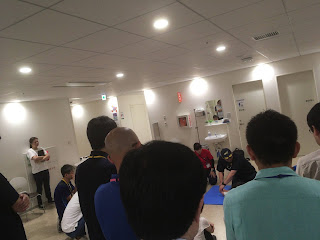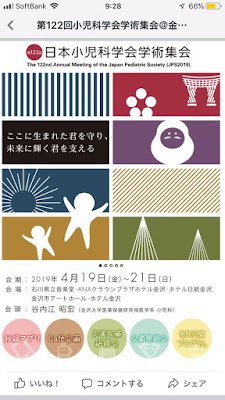他の専門領域との仲間作り!~「災害時小児周産期リエゾン養成研修」参加報告~

新型コロナウイルス感染対策において、神奈川県をはじめ多くの関係者の方々が尽力されています。当院も微力ながら様々な形でサポートできるように院内対策本部を設置して活動しております。 患者さんの容態が1日も早く良くなること、現在隔離されている方々が1日の早くご自宅に戻れること、そして支援活動をされている方々の健康を心より祈っております。 町田です。 先週末に東京医科大学で開催された「災害時小児周産期リエゾン研修」に今年度2度目の講師として参加させていただきました。 ‟災害時小児周産期リエゾン”について簡単に説明します。 現在は大規模災害が発生した際に、被災県の都道府県庁では災害医療コーディネーターを中心に集まったDMAT、日赤など各医療チームが被災地の病院支援や医療搬送を展開していますが、小児や周産期についてはその専門性や特殊性により思うように支援が入れられないことがありました。その際に調整役として都道府県庁に設置された医療対策本部に、小児周産期に関わる相談に乗って調整する役割を担うコーディネーターのことです。 あの話題となった「コウノドリ」にも登場していました。 ちなみに僕は小児科医でも産婦人科医でもありませんが、本講習の「災害医療の基本的考え方-CSCATTT-」という講義を担当させていただいており、自称「救急枠」の講師として仲間に入れさせていただいています。 実際に研修中は小児科・産婦人科の先生方や助産師さん、行政の担当者の方々のテーブルディスカッションをファシリテートする役割もいただいているため、「救急枠」を超えた小児周産期領域の様々な仕組み(医学知識というより地域の医療体制、学会・医会、医師会との関係など)を知る必要があります。 講師という立場で参加していますが、参加するたびに新たな発見とともに小児周産期領域の方々と顔の見える関係が作られることに、この研修に参加することの意義を感じています。そしてこれからもリエゾンになる受講生の方々に、災害医療の基本的考え方をしっかり伝えさせていただきながら、様々な領域が“ONE TEAM”で災害に立ち向かえるように力添えをしていきたいと思います。 ちなみに今回の研修では以前に当院に支援に来られている先生、以前一緒に働いていた先生、大学の後輩との再会もありました。 会場の西新宿は大都...