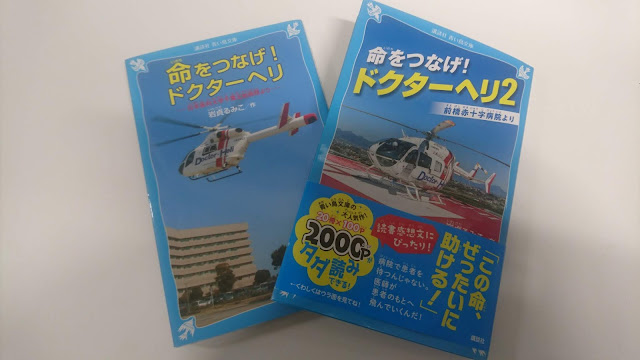院外広報誌「博愛」が「HAKUAI+(はくあい プラス)」に進化しました!

丸山です。 当院では年に3回程、院外の医療従事者・一般の方向けに院外広報誌を発行しているのをみなさんご存知でしょうか。 タイトルは「博愛」。1877年の西南戦争の時に設立された日本赤十字社の前身である「博愛社」に由来するもので、赤十字の精神を体現している単語でもあります。 そんな当院の院外広報誌も2000年に第1号が発行され、早20年。この度、「HAKUAI +」にリニューアルしました!平成から令和、旧病院から新病院へと私たちの環境が変化したことも踏まえ、「博愛」から「HAKUAI+」へと進化を遂げ、デジタル媒体メインの広報誌になりました。冊子での配布は患者さん向けに院内で数十部のみとし、職員への配布をなくすことでエコ・フレンドリーになり、職員が毎日目にする電子カルテのログイン画面(ポータルサイト)に掲載することでいつでもどこでも見られる環境になりました。 この「HAKUAI+」ですが、一般の方々も当院ホームページからも閲覧することができます。当院ホームページを下にスクロールしていただくと「一般の方」と書いてあるボックスの中に、院外広報誌「HAKUAIプラス」と記載されているところがあるかと思います(写真②をご参照ください)。こちらをクリックしていただくと当院の最新版の院外広報誌が表示されます。またバックナンバーもございますので是非ご一読ください。 今回の特集は「コロナと戦う情報システム」です。 当院には情報システム課という部署があり、この部署の方々が病院情報システムを全て管轄しています!詳細は特集をご覧いただければと思いますが、当院では新病院への移転に当たりIT(information technology)を多く導入し、今も尚新しいシステムを導入し続けています。例えば、with コロナ時代の必須アイテム「オンライン会議システム」も今年の初めに導入されました。当院ではCisco Webex meetingというものを採用しています。それぞれが自身のパソコンから参加できるため、現場への滞在が不要になるだけでなく、広い会議室に広角カメラを設置し、院内の参加者においても3密を避けながら会議を行えるようになりました。 また、Cisco Jabberという電話アプリも導入されました。それぞれの医療スタッフが内線番号を持っていて電話ができる点は今まで同様ですが、さ...