ドクターヘリ広域連携の恩恵!~「2019年度第4回群馬県ドクターヘリ症例検討会」開催報告~
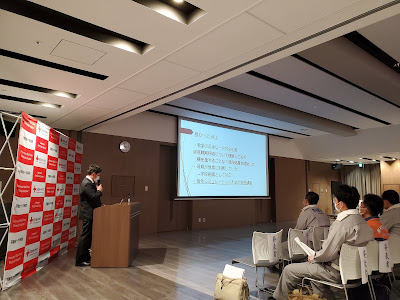
町田です。 昨日当院で「2019年度第4回(通算42回目)群馬県ドクターヘリ症例検討会」を開催しました。 尚、開催にあたっては本会の主催である群馬県ドクターヘリ運航調整委員会、運航主体および会場となる前橋赤十字病院で十分の協議をしております。また参加者の皆様にはマスク着用、手洗いの徹底をお願いし、会場にも手指用アルコール消毒を準備させていただきました。 今回もいつもと同じように、実績報告、症例(事案)検討、運航会社からの連絡という次第でした。 症例検討に関しては、以下の内容の通りです。 「施設間搬送の引継ぎランデブーポイントでショックを呈していた症例」 ・施設間搬送は現場出動より重症率が高いのでより注意が必要。 ・ RP で引き継ぐ予定であっても、救急隊が危険と判断した場合は病院まで医療スタッフ派遣をリクエストしてもよい。 「小児 CPA 症例で救命の連鎖がうまくつながった事案」 ・平時より消防と学校の連携があり、学校職員で有効なバイスタンダー CPR が実施されていた。 ・埼玉県では確実に医師に指示要請できるシステムがあり、遅滞なく特定行為が実施できている。 ・群馬県の指示要請を受ける医療側の体制、小児周産期救急体制について真剣に考えないといけない。 「心タンポナーデを呈した急性大動脈解離の事案」 ・“胸背部痛”というキーワードがあれば、さらに“ 突然発症”“冷汗”“胸痛”など危険なキーワードを伴っていないかどうか指令課員や救急隊から積極的に探りに行く姿勢が必要である。 ・大動脈解離の搬送先は緊急手術ができるかどうかも大切な要素である。 「多数傷病者事案に対して直近災害拠点病院を救護所として利用した事案」 ・ ヘリ到着遅延に対して直近拠点病院を救護所扱いとして活動した。 ・傷病者に先に接触した病院医師にそのまま診療リーダー( Triage, Treatment )を担っていただき、ヘリ医師は搬送調整を含めた全体統括 (Command, Transport) を行った。 また先日館林地区消防組合消防本部で開催した症例検討会(多数傷病者事案、2機のドクターヘリが参集した事案)について、そこで議論した内容とその時出た結論について参加された各消防機関の方々と情報共有...




