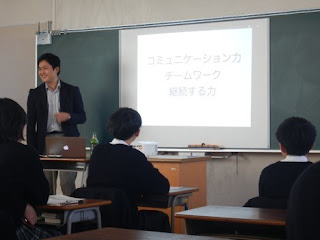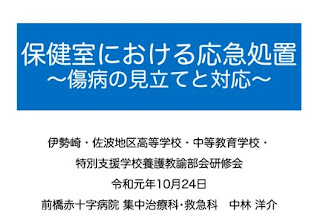町田です。 11月25日に東京の霞が関ビルディング35階にある東海大学校友会館で開催された「HEM-Net創立20周年記念シンポジウム」にパネリストとして参加してきました。 HEM-Netとは“認定NPO法人 救急ヘリ病院ネットワーク”のことで、これからもドクターヘリの全国配備に尽力をしていただき、ここ最近は「D-call Net」や「ドローンとドクターヘリとのコラボ」など新しい取り組みを始めています。 今回のパネルディスカッションは「これからのドクターヘリー問題と解決策ー」というテーマで、以下のメンバーがそれぞれの得意(?)分野で発表を行いました。 <夜間運航> ・全日本航空事業連合会ドクターヘリ分科会 辻 康二 氏 「ドクターヘリ夜間運航に向けてーこうすれば飛べます!」 ・航空自衛隊航空救難団司令部 西村 修 氏 「航空自衛隊航空救難団の立場から」 <地域医療> ・宮崎大学医学部附属病院救命救急センター 金丸 勝弘 氏 「Doc-Heli for All, All for MIYAZAKI」 <周産期医療> ・長崎みなとメディカルセンター地域周産期母子医療センター 平川 英司 氏 「ドクターヘリを活用した周産期母子医療」 <広域運用> ・前橋赤十字病院高度救命救急センター 町田 浩志 「空から見えない県境との戦い~首都直下地震を見据えたドクターヘリ広域連携に向けて~」 <高度新技術の活用> ・日本医科大学千葉北総病院救命救急センター 本村 友一 氏 「救急・災害時のドローンの利活用と課題と展望」 ・株式会社ウェザーニューズ 高森 美枝 氏 「ドクターヘリ安全運航の為のニューテクノロジー」 何度目か忘れるほど同じ舞台に立つことの多い本村先生(写真右)とともに・・・ 災害時のドクターヘリ運用に関する盟友(戦友)です。 そして同じく長いことお世話になっているHEM-Net事務局の小山さん(写真中央)! 僕の発表は災害時のドクターヘリの連携について、今一度原点に立ち返り被災地外のドクターヘリが困っている被災地のためにすぐに動けるような広域連携を平時から築くことの意味について話をさせていただきました。 1998年にドイツで発生した高速列車の脱線事故では「発災直後よりドイツ全土から30機近くの医療ヘリが...