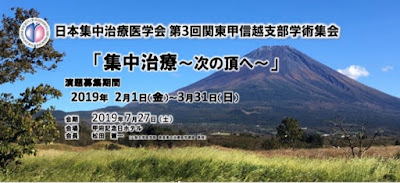現場主義!~『第70回日本救急医学会関東地方会学術集会』&『第57回救急隊員学術研究会』開催報告~

太平洋南岸に発生した低気圧と前線の影響で、群馬県も今日の夕方から明日にかけて降雪の予報が出ています。今年は雪が降ることがほとんどなく特に冬道の運転の心構えがあまりできていない印象がありますので、どうしても運転される方は雪道用のタイヤの確認を行い、雪道での多重クラッシュ事故の引き金にならないように十分注意してください。 1月18日に前橋で行われた『第70回日本救急医学会関東地方会』および『第57回救急隊員学術研究会』の報告です。 本学術集会および研究会は当院中野実院長を会長として、「現場主義ーPre-Hospitalから社会復帰までー」をテーマに開催させていただきました。 この日も今日のように朝から底冷えするような日和で、また会場が前橋駅より通りロケーションであったにも関わらず、1000名を超える多くの方々にお集まりいただきました。 外の寒さに負けないほどの活発な議論が各セッションで行われており、座長を担当していただいた方々、そして発表者、聴衆者のすべての皆様に心より感謝いたします。また本会には全国から著明な先生方にお集まりいただき、各種分野での最新の知見や興味深いお話を聞かせていただきました。 当科からは以下のメンバーが参加しました。 <中村医師> ランチョンセミナー 座長 <町田医師> ランチョンセミナー 座長 一般演題:調査・研究・検証(資機材、活動) 助言者 <鈴木医師> 教育講演 座長 <藤塚医師> パネルディスカッション:局地災害 こうすればうまくいく 座長 「迅速さと連携が局地災害で重要である」 パネルディスカッション:本白根山噴火対応救急医療活動報告 座長 「草津本白根山噴火災害 医療本部活動」 <小橋医師> 一般演題:調査・研究・検証(医師出場、多数傷病者対応) 助言者 <金畑医師> パネルディスカッション:ECMO管理 こうすればうまくいく 「前橋赤十字病院 ECMO センターとしての取り組み」 <永山医師> パネルディスカッション:外傷初期診療 こうすればうまくいく 「高度救命救急センターとしての外傷診療における当院の取り組みについて」 また本会を運営にするにあたり、長期にわたって準備に奔走していただいた当院スタッフ、県内消防の皆様、また当...