レクチャー:多施設レジストリで臨床研究をやってみよう
おはようございます!ブログ担当の永山です。
先日、河内Drに「多施設レジストリで臨床研究をやってみよう」というレクチャーを開催してもらったので、ご報告です。
日々臨床をしていると、臨床疑問(Clinical Question: CQ)にぶつかることがあります。
臨床疑問とは、医療現場で患者に接する医師や医療者が抱く疑問のことです。病態、評価、治療、リスク、予防など、さまざまなテーマがあります。
当科の例でいうと、心肺停止後の低体温療法の有効性、敗血症における輸液の最適化、外傷性脳挫傷の気道管理など、どのように対応すれば患者さんにとって最良の結果を残せるかは、長年議論されていますが、いまだに議論の余地があるところです。
こうした疑問を解決するために臨床研究が行われますが、単施設(一つの病院)のデータを用いた研究では限界があります。そのため、日本全国(研究によっては世界中)の施設でデータを集める研究が数多く行われています。このように、複数の施設で集めたデータのことを「多施設レジストリ」と呼びます。
しかし、多忙な勤務の合間を縫って臨床研究を行うのはなかなか大変です。いざ研究を始めようと思っても、研究デザインの考え方、統計手法、結論の導き方などを組み立てるのは、かなり骨の折れる作業になります。
今回、河内先生が多施設レジストリを用いて、「どのような経緯で研究を始めたのか?」「どのような苦労があったのか?」「 後輩たちが研究を行う際に躓きやすいポイントについて」抜群のトーク力で講演してくれました。
学会等で同様の講演会がありますが、雲の上のひとと感じてしまうので、身近な人の経験談はすごく新鮮で、心に響くものがあります。
キースライドを数枚掲載させていただきました。
自分たちの仕事は診療が主だとおもいますが、臨床研究をすることで、臨床疑問を明確化することで、論文を検索し、それが自分たちが直面している問題にあてはまるか?適応できるか?を考えて最適な医療を提供することが必要です。臨床研究をおこなうとそういった、論理的思考のスキルアップにもなるので、今後も積極的にとりくんでいけたらと思います。
先日、河内Drに「多施設レジストリで臨床研究をやってみよう」というレクチャーを開催してもらったので、ご報告です。
日々臨床をしていると、臨床疑問(Clinical Question: CQ)にぶつかることがあります。
臨床疑問とは、医療現場で患者に接する医師や医療者が抱く疑問のことです。病態、評価、治療、リスク、予防など、さまざまなテーマがあります。
当科の例でいうと、心肺停止後の低体温療法の有効性、敗血症における輸液の最適化、外傷性脳挫傷の気道管理など、どのように対応すれば患者さんにとって最良の結果を残せるかは、長年議論されていますが、いまだに議論の余地があるところです。
こうした疑問を解決するために臨床研究が行われますが、単施設(一つの病院)のデータを用いた研究では限界があります。そのため、日本全国(研究によっては世界中)の施設でデータを集める研究が数多く行われています。このように、複数の施設で集めたデータのことを「多施設レジストリ」と呼びます。
しかし、多忙な勤務の合間を縫って臨床研究を行うのはなかなか大変です。いざ研究を始めようと思っても、研究デザインの考え方、統計手法、結論の導き方などを組み立てるのは、かなり骨の折れる作業になります。
今回、河内先生が多施設レジストリを用いて、「どのような経緯で研究を始めたのか?」「どのような苦労があったのか?」「 後輩たちが研究を行う際に躓きやすいポイントについて」抜群のトーク力で講演してくれました。
学会等で同様の講演会がありますが、雲の上のひとと感じてしまうので、身近な人の経験談はすごく新鮮で、心に響くものがあります。
キースライドを数枚掲載させていただきました。
自分たちの仕事は診療が主だとおもいますが、臨床研究をすることで、臨床疑問を明確化することで、論文を検索し、それが自分たちが直面している問題にあてはまるか?適応できるか?を考えて最適な医療を提供することが必要です。臨床研究をおこなうとそういった、論理的思考のスキルアップにもなるので、今後も積極的にとりくんでいけたらと思います。




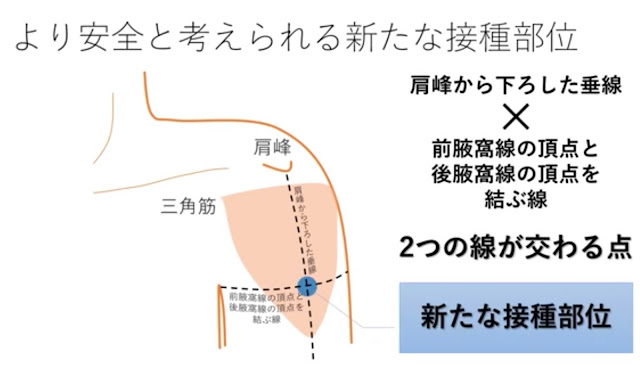

コメント
コメントを投稿
コメントは管理人が確認の上、公開の判断をさせていただいてます。状況によっては公開まで数日頂くことがありますのでご了承お願いします。